示談書の書き方
用紙サイズ・枚数
用紙のサイズや紙の材質に関しては、原則として自由です。
ただし、将来的にもしもトラブルに発展し、裁判所や警察署の記録や証拠資料として綴じられることを考慮すると、公的機関は、すべてA4サイズで統一されていますから、A4サイズで作成された方が良いかと思います。
用紙は、通常のコピー用紙などで大丈夫です。
証拠として残すべき書面ですので、FAX感熱紙などの、保存に耐えないものは使用しないようにされてください。
枚数の制限はありませんが、複数枚にまたがる場合は、ページの抜けやあと足し等の誤解を避けるため、1部毎にまとめてホッチキス等で綴じ、すべてのページとページの繋ぎ目にまたがって契印(割印)をするようにしてください。
示談書の作成する部数
示談書は、当事者の人数分、同一の書面を作成します。
当事者が加害者と被害者の2名であれば2部、3者間の示談であれば3部、ということです。
記載する項目
記載する具体的な項目は、その示談の内容によって異なりますが、一般的な事項としては、以下のようなものがあります。
- 表題(「示談書」「合意書」など)
- 事実内容(事件や事故の日時、場所、など)
- 謝罪条項(謝罪と承諾、免責や宥恕、など)
- 取り決めた合意内容(口外禁止、接触禁止、告訴しない旨、など)
- 示談金の定め(支払う金額の名目や支払方法・支払期限)
- 不履行に関する定め(遅延損害金や違約金など)
- 清算条項(相互に合意した内容以外に請求をしない旨)
- 示談成立日(または示談書取り交わし日)
- 当事者の住所・氏名(自署)、および捺印
なお、署名がなされていて押印が無いという場合や、住所に誤記があるという程度では、示談書が無効になることはありません。
刑事事件などで相手に住所を知られたくないという場合は、住所を伏せて取り交わすことも可能です。
当事者が未成年の場合は、法定代理人(親権者や未成年後見人等)が示談を行う必要があります。
示談書の基本形式
示談書は契約書の一種です。 契約書などの法的文書は、原則として形式は自由とされていますが、齟齬を避けるために、正式な体裁を採ることが良い場合もあります。 日本における、法律、政令、条例、公文書、規則、規定、などの基本的な形式ないし構造は一定の規則が定められておりますので、参考に記載しておきます。
| 1. | 編、章、節、款、目 |
|---|---|
| 条文が多い法令について、条文を論理的な体系に基づいて区分する必要がある場合には、まず「章」で区分します。 章の中を細分化する必要がある場合には、章の中に「節」を設けます。 さらに細分化する必要がある場合にはレベル順に「款」「目」といったものを設けます。 | |
| 2. | 条 |
| 「条」は、本則を構成する基本単位となるもので、原則として、1つの条は、見出し、条名、項で構成されます。 項は必ず設けられますが、古い法令や条文が少ない法令においては、見出しや条名は付されないことがあります。 「見出し」は、条名の前に、その条の内容を簡潔に掲げた字句のことであり、「(○○)」と括弧で括った形で表記されます。 この見出しも法令の一部を構成するものとなります。 現在の法令では見出しの後に改行が入って条名が記されますが、古い法令では見出しそのものがないか、条名の後に改行なしで見出しが付されているものもあります。 見出しは、その条の内容の理解と検索の便のために設けられ、通常は条のみに付されますが、附則が項のみで構成されている場合には、その項に付されることもあります。 また、見出しは原則として1条ごとに付けられるが、連続する複数の条が同じカテゴリーに属する事項を規定している場合は、それらの条群の最初の条の条名の前に一つだけ付されることがあり、これを「共通見出し」と呼びます。 条名は、ある条を特定するための名称のことであり、本則の中で一意に定められる。通常は「第○条」と番号で表記されます。 複数の条がある場合には、第一条から順に漢数字で番号を振ってゆくのが正式ですが、横書きの文書で法令を表記する際に漢数字をアラビア数字に置換する例も見られます。 条と条の間などに新たな条を挿入する際には、その挿入した条の条名に枝番号を付して、「第○条の○」といった形で表記します。 | |
| 3. | 項 |
| 「項」は、条の中に必ず1つ以上設けられる要素で、いわゆる条文が記される部分営業です。 2つの条文から構成される項では、最初の文を前段、あとの文を後段といい、あとの文が「ただし」で始まる場合、最初の文を本文、あとの文をただし書といいます。 3つの条文から構成される場合には順に前段、中段、後段といいます。 項は段落であるため、通常第2項以降にアラビア数字で項番号が付されます。 ただし、項のみで構成された附則や本則で条名が付されない場合には、第1項から項番号が付されます。 各条は必ず第1項から始まり、複数の条の間で連番にするようなことはしません。 また、特定の項を挿入したり削除したりする場合、以降の項番号は当然に繰り下がりや繰り上がりが行われ、条や号のように枝番号を用いたり「削除」と記すようなことはしません。 | |
| 4. | 号 |
| 「号」は、項の条文の中で事物の名称等を列記する必要がある場合に用いられるものです。 列記されるものは名詞ないし体言止めが基本となります。 号の冒頭には号名が付され、通常は漢数字が用いられる。また、号の挿入などの際には条名と同様に枝番号が付されます。 1つの号の中をさらに細分化して列記する必要がある場合は まず、各列記事項の冒頭に「イ、ロ、ハ、…」を用い、 以降、細分化のレベル順に「(1)、(2)、(3)、…」 「(i)、(ii)、(iii)、…」が用いられます。 |
示談書の作り方
示談書の作り方
(1)はじめに
|
示談書の原本(同一書面)は当事者人数分の部数を作成し、それぞれ1部ずつ、左側をホッチキスで綴じます。 ↓下の画像をクリックすると動きます。 |
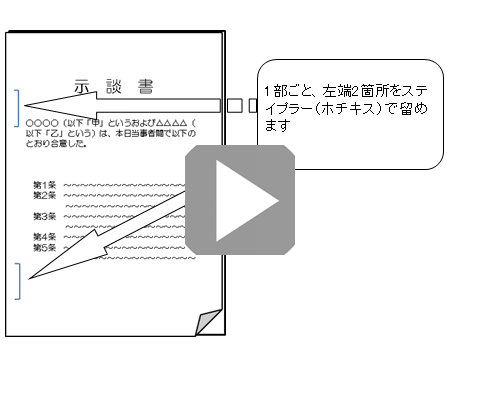
|
(2)署名捺印
|
原本すべてに、最終ページの署名欄に当時者全員が住所氏名を自署の上、捺印します。 また、すべてのページのつなぎ目にまたがって、当事者全員が署名捺印をします。 ↓下の画像をクリックすると動きます。 |
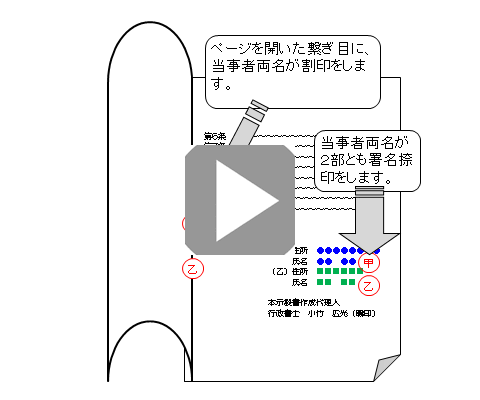
|
(3)示談書原本同士の契印
|
原本すべてを重ねて、割印(契印)します。 原本全てが同一文書であることを示すためのものです。 ↓下の画像をクリックすると動きます。 |
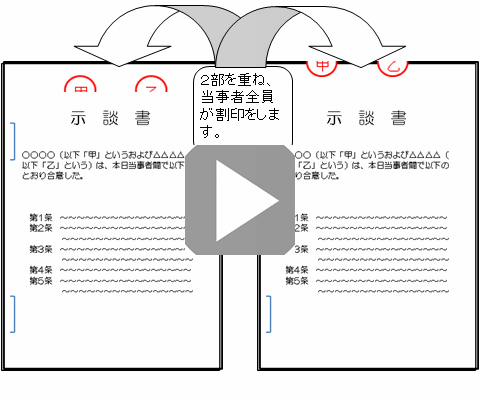
|
以上で完成です。
示談書.net/目次
示談書・和解書について
| 示談書とは?和解書・合意書との違い |
| 示談書を作成するメリット・示談書の効力 |
| 示談書が無効になる場合 |
| 中間合意・確認の重要性 |
| 示談書の書き方・作り方 |
| 示談書に貼る収入印紙 |
| 示談書の送付状(案内文・挨拶文) |
| 示談書の雛形・文例 |
| 示談書の署名捺印、ハンコ・拇印 |
| 相手と会わないで取り交わす |
| 示談書の修正・訂正 |
| 示談書の取り消し・撤回 |
| 示談書を公正証書にする |
男女関係の示談書
| 不倫・浮気 |
| 婚約破棄・内縁解消 |
| 交際解消・人工中絶手術 |
| 認知・養育費 |
| ストーカー |
交通事故の示談書
| 物損事故 |
| 人身事故 |
その他の事故の示談書
| 介護施設事故 |
| 保育施設事故 |
| 食中毒事故 |
| 医療ミス・医療過誤 |
製造物責任・工作物・営造物責任
| 欠陥商品、食品瑕疵 |
| 家電出火(爆発)事故 |
| 設置・修理ミス事故 |
| 店舗内転倒事故 |
| 店舗駐車場事故 |
労働問題の示談書
| 不当解雇・雇止め |
| 内定取り消し |
| セクハラ・パワハラ |
| 未払サービス残業代 |
| 労災事故 |
賃貸借
| 立退き・明け渡し |
| 敷金返還 |
| 重要事項説明義務違反 |
| ルームシェアトラブル |
学校内
| 授業中事故・部活中事故 |
| 喧嘩・いじめ・わいせつ事件 |
| 体罰・虐待・アカハラ |
犯罪被害
| 暴行・傷害・器物損壊 |
| 万引き・盗難(窃盗)・強盗 |
| 詐欺・横領・背任 |
| 名誉毀損 |
| 痴漢、覗き、盗撮、盗聴・不法侵入 |
| 強制わいせつ、強姦 |
事務所概要
事務所概要
| 事務所概要・アクセス |
| 弁護士・行政書士紹介 |
| 費用・メニュー |
| お問い合わせ |
| リンク |
| サイトマップ |